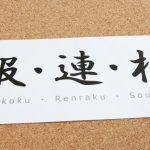会議といってもいろいろあります。
会社で決められたことを伝えるだけの報告型会議などはそこに参加しているメンバーは発表内容を聞いてメモするだけでもよいかもしれません。
しかし公式な会議であっても少人数で臨時的に行う軽いミーティングであってもそこに参加する以上、何らかの発言をすることはビジネスパーソンとしてたいへん重要なことと言えます。
なぜなら会議で討議されたことによって参加メンバーの行動が定義されるからです。
言い換えると、会議で決められたことをよりどころとして行動をしていかなければならないと言ってもよいでしょう。
最初から最後まで一言もしゃべらずにただその場にいるだけでは本当に賛成しているのか反対なのに意見を言わないのかわかりません。
賛成なら賛成、反対なら反対とはっきり自分の考えを表明すべきでしょう。
誰かが言ってくれるからわざわざ自分から言わなくてもということではいけません。
と、こんなことはわかっているのですが、実際には何も言わずに会議が終わるのを待つことも多いのではないでしょうか。
そのようなことになる理由はいくつか考えられます。
1.討議の進行にについていけない。自分の専門外だからよくわからない。
2.声の大きさで決まってしまうのでどうせ自分の意見など反映されるわけがない。
3.勇気をもって発言してもトンチンカンなことを言ったら恥ずかしい
<討議の進行についていけない。自分の専門外だからよくわからない>
これはやはり勉強不足ですね。
会議の参加メンバーとして選ばれた限り、当事者であるわけですから少なくとも議題について最低限の予備知識をもっておかないといけないでしょう。
「専門外だから」というのは言い訳に聞こえます。当事者としての責任を自覚することが大切です。
<声の大きさで決まってしまうのでどうせ自分の意見など反映されるわけがない。>
これもある意味責任逃れのようです。
たしかに特定の人の一声ですべてが決まってしまう会議もあるかも知れません。
しかしそれでも言うべきことは言う。そして結論を出すための筋道をせめて明らかにさせた上で決まったことには従うという態度が好ましいです。
<勇気をもって発言してもトンチンカンなことを言ったら恥ずかしい>
これは根が深い悩みです。
自分だけが目立ちたくない。
周りの意見を違うことを言ってしまったらどうしようか。
全員の意見に迎合しておくのがいちばん楽だし安全だ。
日本人の特性としてよく言われる「みんなと同じ」でなくてはいけないという気持ちからでしょうか。
自分の意見に自信がないために発言できない場合は、自信をもって発言するために考えをまとめる訓練をすればよいですが、皆と食い違うのが嫌だという場合は考え方を根本から改めないと難しいと思います。
それではどのような考え方をすればよいのでしょうか。
それは「人は皆違う」ということを認めることです。
そして「皆違う」ことを前提に、コミュニケーションを行うことで全体の合意(コンセンサス)をとりつけるという習慣をもつことが非常に大切です。
人はそれぞれ生い立ち、価値観、性格などが異なりますので10人いたら10人ともすこしずつ違う意見や感じ方をもつのが当たり前です。
「違って当たり前」という考えをもつことができるようになると「人と違ったらどうしようか」というストレスがなくなり精神衛生上もたいへん好ましい状態になります。
また「違って当たり前」ということを前提にコミュニケーションをとることになりますので発信と傾聴、賛意と反論、確認と再検証などをくりかえし、結果的にコミュニケーションの達人となります。
ストレスなくコミュニケーションを行う習慣をもつことはその人の人生そのものを幸せなものにすること間違いありません。